アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合


私は以前から地下や洞窟のような空間にどこかで憧れてきました。意識していたわけではなくて、無意識に洞窟のような空間をつくってしまう。自分が頭でどんなに軽い空間をつくりたいと思っていても無意識に表れてしまう身体感覚のようなものかもしれません。今から30年前、1976年の作品で「中野本町の家」という私が建築家として出発したばかりの頃に設計した住宅があります。私の姉の家族が住んでいたのですが1997年に取り壊されてしまいました。建てられてから21年後に取り壊された理由が、洞窟と密接な関係があると思っていますので、プロローグとしてご紹介します。

実はこの住宅を設計している間、私は内部にしか関心がありませんでした。外部から閉ざされた内部空間を美しくデザインすることに没頭していて、その結果として「中野本町の家」の外部はコンクリート打ち放しの壁が露出して、エントランス以外は道路方向に面した開口部ははとんどないというものになりました。ですから間もなくツタに覆われて外部が隠蔽されていった時に私は何かホッとしたような気持ちでいました。
当時ずっと考えていたことは開口部からの光を敢えて抑えて、特定の場所からだけシンボリックな光が入ってくるような空間をつくろうということでした。断面を切ると単純な片流れの形が現れるのですが、天井と壁との間を左官のプラスター壁でならして小さなRを連続させると平面的にも小さなカーブがいくつか現れます。そうやって内部性、今になって思うと洞窟性を高めようとしたわけです。多木浩二さんがはじめて私の建築を見てくださったのも「中野本町の家」だったのですが、『新建築』の評論で、「白い闇」という表現をされていました。そういう地下空間のような建築でした。そして夜になると床面に設置したライトによって壁に影が映し出されるのですが、見方によってはラスコーの洞窟の壁画のようなものになります。
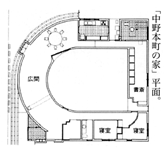
この住宅がつくり出した外から閉ざされた内的世界は、住人にとって家族の関係を強める結果になりましたが、20年という歳月を経て、彼らは外の世界に出ていきたいと思うようになりました。特に当時、小学生だったふたりの姉妹は20年後には20代後半になっていて自分たちで自立するためには、この家を出ていかなくてはならなかったのです。家族三人で議論に議論を重ねた結果、家を取り壊して、それぞれの生き方へ移っていきました。
ここで起こったことを考えますと、洞窟の空間が持っている意味がより理解していただけると思うのです。ただ単に洞窟をつくるだけなら美しい内部空間はいくらでもつくることができる。ところが建築とは常に社会の中に存在し、公共性の強い空間になればなるはど社会に対して持っている意味は大きくなる。その時に建築について何を考えなくてはならないか。それが今日ご紹介するふたつのプロジェクトのテーマなのです。