アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合


「水/ガラス」では日本の庇とか縁側という話をしましたが、次は能楽堂のプロジェクトです。私がいちばん好きな能楽堂は、京都の西本願寺の南能舞台です。どこが好きかといいますと、まずひとつは屋外にあるということです。舞台が屋外空間の中に置かれている。もうひとつは舞台と橋がかりの前の白い砂が敷かれた白州と呼ばれる空間がとても広い。それがたいへん気に入っています。それに対して最近つくられている能舞台の多くは室内にあって、舞台の回りに白い砂の広がりがない。これでは、能の空間としての感動が伝わってこない。西本願寺の能舞台のような空間をつくれないかと思ってつくったのが、宮城県の登米町というところにつくった能舞台「森舞台/登米町伝統芸能伝承館」でした。
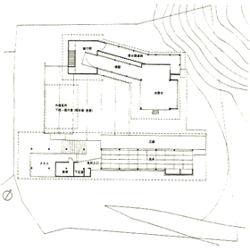
まずここでは舞台を屋外化する。それが第一に考えたことでした。もうひとつは舞台と見所の間を広く取って、その間の空間が裏の森につながっていくようにしたかった。ここはそれを思い切って黒い砂にしたんです。普通は白州というように、白い砂を敷くのが当たり前なんですけれども、ここでは黒い砂で森の中に連続していくような闇をつくりたいと思ったわけです。
舞台に向かって左側のほうは段々になっていて、その下に能の資料館をつくっているのですが、段の縁をステンレスのフラットバーで押さえてスパっと切り、ちょうど水面が滝のように流れ落ちているようにしました。これは「水/ガラス」の水の扱いと同じです。また、普通は舞台の下の部分には腰板がはまっていますが、ここではそれを取っています。腰板がないのは水上の能舞台だけの作法なんです。ここでは黒い石を水と見立てて、水面の中に能舞台だけがフワッと浮いているような感じにしたかったので、腰板を取っているのです。
舞台があって見所があり、その間に森の空間が流れ込んでいます。ふたつの向かい合うものがあって、その間に何かが流れ込んでいるというような空間が、僕の中では原型としてあるように感じています。単体としてのオブジェクトがあるのではなく、亀裂があって、亀裂の中に外のものが流れ込んでくるという、いわば雌型のあり方、といっていいかもしれません。先ほどの「亀老山展望台」もそうですし、あとでお話しする「石の美術館」もそうです。全部共通して、亀裂のようなものがある。亀裂の中で意識がさまざまな体験をする建築のあり方があるんじやないかと考えています。

町のほうから能楽堂を見ると、スギの間伐材を使ったルーバーになっています。かすかに向こうが透けて見えるという感じをつくっています。ルーバーというのはすごく面白くて、角度とか光の状態によって、完全に透明になったり、板状のものに見えたりと、見方によって全然達います。そういう物質性が面白いんですね。時間の中の物質性といってもいい。時間によってまったく変わって見える物質性、要するに写真では伝えきれない物質性というものがルーバーにはあります。そういうところがたいへん魅力的で、このあと、ルーバーが頻繁に出てきます。