アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合


次は「石の美術館」とある意味で似ているところがあります。石というと非常に重たいものと思われがちですけれども、物質性というものは逆に軽やかなディテールを媒介としてではないと伝わらないのではないかと僕は基本的に思っているんですね。物質性を重たいディテールでつくってしまうと、ディズニーランドみたいなフェイクにしか見えないわけです。軽くしたときに初めて、物質というのは正体を現してくれるという思いがあります。ここでは木なのですが、木を使って思い切って軽やかな建築をつくりたいと考えました。

建物は安藤広重の収蔵品のある「馬頭町広重美術館」という建物で、屋根も壁も全面、木のルーバーでできています。ひとつのマス、単純な切妻のかたちが全部ルーバーで覆われてつくられている。建築の実務経験のある方は、どうして屋根に木が使えるのかと計しく思われるでしょう。ひとつは、建築基準法に、屋根は不燃材でつくることと書いてあって、燃える木では屋根はつくれない。もうひとつは、木を屋根の上に置いたら腐るのではないかという、ふたつの疑問をもたれたでしょう。何とか腐らなくて燃えない木はないだろうかと昔から思っていたら、それと同じことを考えていた人が宇都宮にいたのです。
安藤寛先生という林野庁の役人だった方です。役人のときにスギの木をいっばい植えたけれど、でもそのスギが今や全然使われない。スギを使えるようにするためには、腐らなくて燃えない加工をしなくてはいけないということで、研究されていました。今はもう七十歳を過ぎている先生ですけれど、その方がずっとしていた研究と僕のしたいことがドッキングして、初めて建築で燃えなくて腐らない木を使った屋根というのができたんです。処理の仕方は、遠赤外線の処理で木の導管の中を薬剤が浸透しやすいようにして、そこにホウ酸塩とリン酸塩を注入し、中で結晶化させるという方法ですので、ほとんど見た目は無塗装に見えます。建築センターから不燃相当という認定をもらってやっと実現したのがこの屋根です。
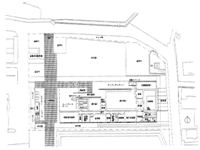
ルーバーの角材は全部30ミリ×60ミリでピッチは120ミリです。全部同じピッチと寸法でつくっています。屋根のルーバーと天井のルーバーとが二重になっていて、その間に、光が入ってよいところはガラスのルーフが挟まっていて、光が入ってはいけないところは鉄板のルーフが収まっている構成になっています。
柱はムクの鉄の75ミリ×150ミリが基本寸法になっています。地震力は建物の鉄筋コンクリートの部分が受けもち、柱は鉛直加重だけを受けることになっているので細いんです。それから、柱がサッシュを兼ねることによって、サッシュをなくしたものですから、全体に透明感が出る。さらにガラスを外側から押さえる押縁もなくして、ガラスのツルンとした面だけで表面をつくりたいと思ったので、ガラスと柱の間のジョイントを工夫してあります。庇の出は3,600ミリと深くして、その庇を出す構造体もなるべく細いプレートを使っています。
ディテールの話は専門的でつまらないと思われるかもしれませんが、そこが実は物質性を扱うときにはたいへん重要なのです。ディテールが甘くなると、物質性のもっている緊張感がなくなってしまう。実は自分でもこんなにディテールにこだわることになるとは思っていなかったのですけれど、物質性ということをやりだすとディテールを考えざるを得ません。

内部では壁に和紙を使っていますが、この和紙の壁は、そのままでは指で破かれてしまうので、実はその後ろにワーロン紙という薄いプラスチックのシートを被せてあります。最近の建築に自然素材がなぜ使われなくなったかというのは、弱いとか燃えるという問題があるからです。弱いものがどんどん排除されています。弱い自然素材はもうほとんど死に絶えていくわけです。それに対して、先ほどの高柳の和紙もそうですけれども、僕は弱いものを使いたい。しかしそれを使うときには少し強くしてやらないと、今の社会の中で受け入れられない。ある意味ではそれがテクノロジーということではないかと思います。だからテクノロジーに対してかなり興味をもってやらないと、自然素材というのはそもそも今の社会から排除されるような仕組みが出来上がっているわけです。
広重美術館みたいな単純な形態の中にシークエンスを畳み込んであるような建築は、ビデオのような時間軸のあるメディアでないと、全体性は伝わらないと思う。その意味で、簡単に写真が撮れてしまう建物よりも、時間軸に沿ってあるシークエンスが流れていくことで初めて伝わる建物のほうが、今はむしろ面白いのではないかと思うのです。