アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合

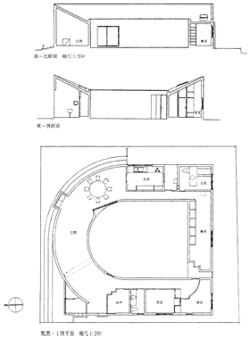
インタビユーで三人は、この家についてまったく別の視点からそれぞれ語っています。私の姉自身は、この家をつくるときに亡くなった主人への思いが非常に強かったものですから、姉との会話が進行するにつれて、家が閉ざされていく方向に増幅していった感じです。普通のクライアントなら、「そんなに窓をなくすことはやめてくれ」というのが普通でしょうけれども、むしろ窓をなくして光を採り入れる方向に進んでいきました。
一方、二人の子供は当時小学生でしたから、ほとんどなにもわからないままこの家に住みはじめました。長女は、この家に対して、あるときからかなり批判的になり、一番早くこの家を出ていきました。大学を出てシェフになろうと、和風の割烹にいって修行をはじめました。自分の母親がこの家の空間に籠もっていることに対して、非常に批判的でした。この家を捨てて、もっと別の生活をしたほうがいいと考えていました。長女はこの家をお墓のように感じていたということです。私にとってはショッキングな言葉であったわけですが、ある一点に向かって屋根の勾配が降りて、閉ざされた黒土の中庭は、まさしくお墓を象徴するようなモニュメントであったと彼女が考えたのも不思議ではないでしょう。
一方、次女は、物心ついたときにすでにこの家にいました。真っ白な壁の中を駆け回っていて、床に置かれたランプにつまずいて母親に叱られたり、あるいは壁を汚して叱られた記憶がありました。彼女は皮膚から空間を感じ取っていました。したがって、彼女は最もこの空間に対してシンパシーを示していたわけです。自分の美意識は、すべてこの家から形成されたと語っています。
姉は音楽の仕事をしているのですが、都内の別の場所に小さな仕事場を構え、やがて夜も仕事をするようになり、そのままそこで泊り込むようになりました。結局、次女が一人で家にいる状態が増え、彼女自身も大学を卒業して勤めはじめると、この家を一人で守ることにギブアップして三人でこの住宅をどうしようかと議論を続けました。その議論には時どき私も参加させられて意見を求められたわけですが、結局、三人ともこの家を出ていって自立することになりました。そして、愛僧半ばするこの住宅が人の手に渡って存在し続けるより、なくなってしまったほうがいいという結論に達し、壊すことになった次第です。現在、その敷地いっばいに小さなマンションが建ち上がりつつあります。 どうしてこの家が壊されたのでしょう。家は家族の肖像であるといわれます。設計者が勝手に設計しても、できあがった家は家族の顔を示す。これは当然のことだと思いますが、この家の場合には住むための容器としての家というよりは、家族という絆を強く象徴するような空間でなくてはならなかつたと思います。
住宅は、機能によってつくられる住むための器という部分があるわけで、この住宅にほかの人が住んでも、それなりの機能は備えて住んでいくことはできます。しかし、この家の場合には、この家族だけの特異性を、ほかの家よりもう少し強く持ってしまったためにこの住宅がここの住人と同じように生まれて死んでいく運命を辿ったんだと思います。