アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合







今でも手割りの石はあちこちでつくっていますし、手吹きのガラスもあるわけですが、大きな板を割り出す技術は終わってしまったのです。
製材する前の時代に使っていたのは前挽大鋸(まえびきおが)といって、現在でも特別な木はこの前挽大鋸で挽きます。たとえば銘木ですが、銘木というとケヤキの直径一メートルくらいのものがあるわけです。しかし、いい目の取れる場所は、ごく一部なんです。そこを本当に上手く取るためには機械製材ではリスクがありますから、少しずつ、要するに剥ぐように取るんです。巨木になりますと、山の斜面にあって、切り出せなかったりしますと、木こりが立木を挽くんです。銘木というのは畳一枚何百万円もするわけですから、その部分だけ現場で切り出して、ヘリコプターで出す。前挽大鋸は今はそういうとさだけにしか使わない。柱はナタやマサカリで、四面を削ればいい。ところが板は延々と挽かないといけない。
前挽大鋸は中国から来ましたが、縦挽きのノコギリは鋼で薄く、長大だから、つくるには刀よりもたいへんな技術力がいるんです。日本の場合、鎌倉・室町時代より前にはなかった。ではその前はどうやっていたかっていうと、板を職人さんが割ったのです。ノミで割ってつくっていた。ですからノコギリ以前はたいへんなんですね。法隆寺に行きますと、板が張ってありますけど、あれはたいへんな努力をして、割ってつくっていたのです。
ぼくも厚い板を割ってつくってみたい、と思っていたのですが、なかなかそういう機会はありません。ところが、秋野不矩さんという、今度文化勲章をもらった女流画家がいらっしゃって、九十二歳くらいの方ですが、彼女のふるさとである静岡県の天竜市が美術館の企画を立てたときに、たまたま彼女が「守矢史料館」を見て、ぼくにやってほしい、ということで市に推薦してくださったわけです。地元はスギがたくさんある町ですから、そこで試すことにしたんです。
秋野さんのご子息は、陶芸家ですから、モノをつくることが好きで、地元が用意してくれたスギの丸太をいっしょにクサビで割ったんですが、とてもたいへんだったんです。まず八センチ角のクサビを打ち込んだんですが、一メートルくらいのものですが割れないんです。さらに割るために、仕方なしに木のクサビを打って、ようやく割りました。なにしろクサビが入ったまま、動かない。ピチピチ音はしているんですが、やっぱり生のスギだったのがいけなかったのかもしれません。

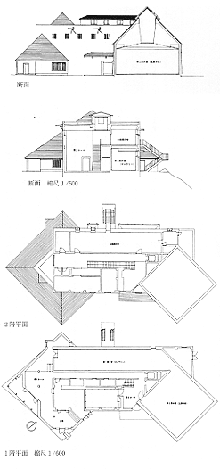
天竜の美術館ですが、山の中ですから、敷地は平らなところがありません。尾根の先端につくっています。本当は割り枚が簡単にでさたら、全部それにしようと思っていました。でも到底不可能だとわかって、せめて製材したときの表面をできるだけ荒くしたいと思ったんです。昔の板を見ると相当荒くノコギリの目が走っていますが、聞いてみたら、今のノコギリではだめだという。どうしてもきれいにしてしまう方向に時代が進んでしまったからです。
屋根は鉄平石です。テラスの柱はチェーンソーで削ったものです。テラスの手すりの板も、素人でできることはできるだけやろう、とぼくたちでやりました。スカート状の板は雨にあたって、色がだいぶ変わり出しています。本当はもうちょっと荒挽きにしてほしいんですけども、やっぱり板を納入する人が、きれいな板を入れるんです。
純粋な土壁は無理だとわかっていたので、それに近い感じの荒々しさのある壁をつくりたいということで、いろいろ工夫をしました。ケイ藻土を自然の土だと思って使ってる人がいますけど、あれは化学物質で固めてありますから、火に当たるとガスが出るはずです。自然の土は、冬、雨がかかったときに凍って崩れるんです。そこで崩れない壁をつくるために土にいろいろ混ぜて実験しました。しかし、結局、ぼくがやったのは、色つきのモルタルにワラを入れて、それを塗る方法です。その表面に土をつけています。
雨樋は目立たない竪樋の予定だったんです。でも排煙窓が並ぶ関係で裏側には出せないし、鉄管の雨樋はちょっと困る。ご存じだと思いますが「ロンシャンの教会」というコルビュジエの名作があります。象の鼻といわれているコンクリートの目立つ雨樋があるんです。それに学んで目立たせてしまおうと、ヒノキとサワラの丸太を削って、内側を防水して取り付けました。ですからこれも手づくりです。
土壁には、さっきもいいましたが、白セメントと色粉と砂とワラを混ぜて使いました。この調合は多くの人から聞かれます。そうしますと、ほとんど土と同じになります。ただ、美術館ですから三階建てくらいの高さがあって、これだけの壁面を塗るのに三日くらいかかる。すると塗る日の天気で色が変わってくるんです。それで、土を水に溶いて泥水をつくって、三パーセントの左官用の糊(ハイフレックス)を入れて、刷毛で擦りつけました。そうしたらきれいに下地にくっついてテカリもないし、表面は土の粒が荒っぼくついていますから、見た目が土なんです。これは冬を二度迎えていますけど、凍結融解で、表面の土が落ちていません。われながら大成功でした。

玄関ホールの柱は、不矩さんと山で選んできた三十二メートルのスギの大木です。その一本を三本に切っていただき、荒々しく仕上げたかったので、チョウナで削ろうとしましたが、これくらいの高さの柱は遠くから見るとチョウナの跡でも、ツルツルに見えるんです。仕方がないから、ぼくと秋野さんのご子息とで、三日かかってチェーンソーで削ったんです。ところが生木ですから、表面が乾くに従ってどんどん有機物が出てきて汚くなるんです。
そこでステインをかけようか、柿渋にしようか、現場ではすぐそういう話が出てきます。どちらもイヤだ、どうしよう。いっそのこと、燃やしてしまおうと思って、現場主任さんに、燃やしたいといったのですが、彼はキョトンとしてるんです。エッ燃やしたいってどういうこと、というので、ただバーナーで燃やしたいんだといったら、しばらく考えてそれは困るというんですよ。火事にならないことはわかってるわけですよ。でも、精神的にせっかく組み上げたものを燃やすのはイヤだというのです。だけど、ぼくも精神的に燃やしたいと思っているといったんです。すると主任さんは、組み立てる前だったらいいというんです。結局、組み立てる前にバーナーで燃やしたんです。そのせいで組み立てるとき、職人さんが燃やした柱に触ると手が黒くなるっていうのでちょっとたいへんだったんですが、それでもちゃんとできました。白い漆喰の壁にこれが立っています。
主展示室には白大理石の原石をそのまま、厚さ七センチに挽いていただきましたが、だいたい畳一枚分の大きさがあります。人がひとり寝るのにちょうどいい大きさなんです。それを床暖房にして、隙間に白セメントを詰めました。壁から天井は漆喰を塗っています。
ものすごく、思わぬ成功をしたのが照度です。普通、照度は上が高くて下が小さくなるのが当たり前のことです。ところが、乱反射と下からの反射があるんです。床からの光がもう一度当たりますから照度が一定している。すると額の影が下にまったく落ちないんです。悪い照明ですと、額の上の出っ張りが絵に落ちる。さすがに注意深い人はそういう照明はしないんですが、それでも額の影が下の壁に落ちて、気になります。実際に見ていただくと、額の影のでない絵が、どんなに爽やかに見えるかわかるはずです。
ギャラリーは片面展示で床に籐ゴザを敷いてあるのですが、これがまた最初はたいへんで、靴を脱いで美術館に上げたいと望んだんですね。すると、やはり建設委員会の方々に、公共の美術館では靴を脱がないっていわれるわけです。


ヨーロッパの美術館では、授業の引率の先生が説明をするとき、子どもたちを土足の床に座らせて、その後ろを普通の人たちが歩いていくというかたちを取ります。あるいは画学生が、邪魔にならないように座ってスケッチしてるわけですね。それはすごくいい感じがして、やっぱり座れるほうがいいと思いました。ところが日本人は土足のところには座りません。やっぱり自由に座ったり寝そべったりできるようにするには、土足をやめたい。だけど、なかなか前例がないといわれるとぼくも困って、ふと理屈を思いつきました。

秋野不矩さんは日本画家なんです。「日本画を土足で観るのはいかがなものか」、といったら、それはそうだ、昔はそういう絵はみんな畳の上で覿たもんだ、という話になって、みなさんに納得してもらえました。どんなにいいことでも、何か頭の中にある観念と違うとみんな躊躇するんです。幸い土足で日本画を観てはいかん、ということを納得していただいて靴を脱いでいます。市も管理がすごく楽だというんです。日本画は油絵と違って、絵の具が微粒子ですから、土ぼこりは大敵なんです。長期的にはそれが問題になるんですが、ここではそれがない。
表皮のところはちゃんと八センチ開いていても、真ん中から先はビクともしないわけです。割った後、協力してくださった材木屋さんに、カラカラに乾かすともっと簡単にできるっていわれました。
無節の相当いいスギを用意していただいたんですが、やっぱり荒く割れるんですね。こういうやり方をしたと文献でわかっていても、やはりこの割れ肌の乱暴さを見ると、ちょっとびっくりするわけです。それを使ってテーブルをつくったんですが、荒々しいんですね。コップが倒れるという機能上の問題がありますが、なかなかいいものです。今、天竜市の美術館のホールに収めてあります。 半分に割って、一本の木から二枚しか板が取れないわけですよね。横から割ろうにも半月状になってしまうので引っかかりませんし、やっぱり無理なんです。一本の木から二枚の板を取ったことになるけど、ちょっと信じられないことです。要するに一本の木から、わずかな板を取るために割って、それ以外は全部削りカスになってしまうわけですから、そうかもしれないし、昔の人にはもっとわれわれの知らないとんでもない方法が、いろいろあったとも考えられるわけです。

その謎が解けたんです。その後、専門家の人たちといろいろしゃべったりしていたら、しばらくして、岡山県へ呼ばれました。国の重要文化財で鎌倉時代末くらいじゃないかと思いますが、神社の床を剥いだら、床の板の裏側がデコボコであることがわかった。表はツルツルで、縁の下のほうがデコボコなんです。これがまさしく割り板だったんです。根太のところだけ削って、縁の下の見えないところだけは割ったまま残したわけです。それが教室ひとつ分くらいの床面にあったのです。それで、文化財の修理の人たちに、割り板について謎がひとつあるので、年輪を合わせてほしいといいました。彼らは年輪を調べていって、どれとどれが組になるかを合わせてくださった。そうしたら、やっぱり一組ずつしか合うのがないんです。やはり昔の人も一本の木から二枚しか板を取っていなかった、ということがわかったわけです。ですからかなり無駄を出して、たいへんな努力をして板はつくられていた。
もうひとつわかったことは、法隆寺とか古いお寺の板が全部無節なんです。生き節がありますと、生き節というのはまわりが枯れてなくて完全に木と一体化した節なんですが、それがボルトと同じ働きをして割れなくなります。日本の木造建築には、無節信仰のようなものがあるわけですけれども、元を辿ると、おそらくそのへんからきたのではないかと思います。