アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合

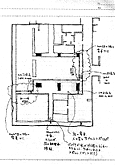
ルイ・ヴィトンの仕事は、ときに中の構成にもタッチすることができますが、多くの場合は外装だけです。はじめは装飾をやるのはイヤだなと思っていたんですが、そのうち表面を使って奥行のあるヴォリュームを見せるのではなく、表面は表面としてテーマになり得るかもしれないと思えるようになってきました。
去年の終わり頃に、美術の作品をつくる機会がありました。東京では国立近代美術館を、大阪では国立国際美術館を会場とした展覧会で展示したU-bisがそれです。東京の会場では、ユニヴァーサル・スペースを仮設壁で各作家ごとの展示空間に分けているのですが、僕は仮設壁の中を広げてもらってそこを展示空間としました。

入っていくと最初からその隙間の展示空間が見えています。ふつうは仮設壁の中の空間と、仮設壁によってできる展示室とはプライオリティがあって、もちろん展示室のほうが重要です。しかし、ここは隙間の空間にすぎませんが、劣勢にある隙間も展示空間と同じぐらいの力をもち得ることができるのではないかということをやっています。もちろんまったく同じ質で同じカになってしまったら同じ展示空間になってしまうので意味がないですから、隙間なんだけど展示空間と同じくらいの力になる方法を考えてみました。しかも隙間には扉がなくて最初からそこに隙間があることがばれているようなつくり方をしています。
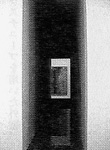
中の壁や天井を大きな花柄で覆っています。壁紙の花柄を700倍にしたものを貼っています。映像で撮ると広角レンズなので柄が柄としてわかりますが、実際に目で見てみると柄というよりは色が点々としているように見えます。このつくり方は装飾以外の何物でもないわけです。ある角度から見れば百合の花とわかりますが、これだけ大きくなると全体として色の表面にすぎなくなります。同じ柄でも小さいまま覆ったものと700倍にしたものを覆うのとでは、まったく違うものになる。装飾というのはまずスケールを変えることで、それが与えてしまうことがまったく違ってくきます。実際に700倍も拡大するとピクセルつまり粒子が見えてくるわけです。これは確か1センチメートル角ぐらいがピクセルになるもので、しかし、そのひとつひとつのセルがひとつの色ではなくてグラデーションになっているので、碁盤の目のグリッドは見えるけど色としてはつながって見えます。この美術作品をやってみて、装飾をやるというのはスケールのことを考えることなのだと思いました。
内部に設けた隙間からちょっとだけ見えるところに絵画を掛けさせてもらいました。これは美術館が所蔵するコレクションの中から僕が選んだもので、辰野登恵子さんの絵画です。壁紙が何重にも貼られたり剥がれたりしていて、そこに柄そのものではなく何かじっと見てしまうようなものを感じたのではないかと思い選ばせてもらいました。
