アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合


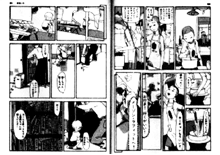
さて、最初に建築を「毒」として捉えたい、といった時、「毒」というのは気づいたら体内に取り込んでいるというようなものであり、そうした行為の受動性に興味があるのだといいました。覚えていらっしゃいますでしょうか? 私はそれに加えて、その「毒」を取り込んでしまう行為そのものも、非常に興味深いものがあると思っています。その行為には、「いつのまにか、何かをしてしまっている」というように、時間の概念が盛り込まれているからです。
私の大好きな漫画に高野文子さんの『黄色い本 — ジャック・チボーという名の友人』(講談社刊)というものがあります。寡作で知られる高野さんですが、読まれたことのある方も多いと思います。ストーリーはびっくりするほど単純で、主人公が、ロジェ・マルタン・デュ・ガールの『チボー家の人々』を読みふける、ただそれだけのものです。あわただしい日常的な時間と、物語世界に没入するという非日常的な時間が、主人公の女学生の生活の中で何度もオーバーラップする様子が描かれています。
お手伝いをしていても、物語世界を思い出して、フワーッとそちらの世界に思いが向いてしまう。いってみれば、白昼夢のような体験なのですが、そのフワーッとした感じが、本当に、美しく描写されています。日常と非日常の間にある境界線が見えてこないのです。
あらためて思えば、私たちは論理的な思考をする際に、日常と非日常といったように何かを対立させて考えることが多いわけです。しかしこのシーンからは、そうした二項対立的なものというのは本当にあるのだろうか、そういうことを考えさせられます。つまり、何かを思考するためにわざわざ対立概念をつくっているだけなのかもしれない、とすら感じるわけです。建築でも、外/中、パブリック/プライベート、などなど、二項対立的に語られるものはとても多いわけですが、何かそうしたものを対立させることなどいっさやめてみるべきなのかもしれません。なぜなら、この高野文子さんの漫画が表すように、それらはもっと緩やかにつながっているかもしれないからです。
建築は、外と中といったように、さまざまなものを切り分け境界線をつくってしまいますが、その境界線のつくり方自体をもっと繊細にしたいという希望は、今、多くの人が感じていることだと思います。そうした気持ちを象徴するモチーフとして、たとえば地形の利用というのがあります。地形というものは、明確なラインをもたない境界をつくる方法というか参照項としてとても魅力的なものです。しかし、そうしたやり方は慣習的な建築に見られないため、新/旧の対比が生まれてしまい周囲から際立ってしまいます。中と外だけでなく、こうした対比すら、私は避けたいと思っています。どうやら私は建築をできるだけひそやかに、つまり、「いつのまにか」変化させる、そうしたことができる方法をずっと探しているようです。
以上のような気持ちが自分の中にあることがわかったのは、「Dior GINZA」や「LOUIS VUITTON TAIPEI BUILDING」のような外装の設計の時ではなく、店舗の内装の設計をいくつかやっているうちのことです。