アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合


部分というと、かなり抽象的というか、あるいはすごく技術的な感じがします。また部分と全体というと哲学のほうでいわれるむずかしい面も出てきます。ただ、単純化していうと人間がものを考えるプロセスでとても重要なことは言葉だと思います。たとえば日本語で窓、あるいは英語でウインドーといった場合、それに付帯している非常に多くの意味を、それもあっさりと単純化して指すことになる。それが建築の部分として確定します。こうした言葉によらない方法で、たとえば技術などの別のカテゴリーで建築を切っていく場合には、窓という言葉が部分にならない場合も出てくる。ただ、その言葉の中で生活と表裏一体になって長い間使われ、残ってきた言葉が現在も使われているわけです。たとえば技術的に開口部といってしまうと、窓も含むしドアも含むのですが、窓という言葉があり、ドアがあり、玄関という言葉があるときに、それぞれ指しているものは総合としての開口部とは異なる。そうしたものが集まってひとつの建築ができているわけです。そうしたひとつひとつの部分に、非常に多くの歴史的な意味合いがあって、それが集積して建築になっている。そうすると一体、部分と部分はどういう関係になっているのか。きしみ合ったり妥協し合ったりしていっているのでしょう。その中で、ある部分にかなりの荷重、あるいは自分の思い入れをかけてやっていくことによって、そういう部分を自分なりに学習していけるんではないだろうかと考えたんですね。ちょうどそれが、吉武研での建築の使われ方の研究と対をなす、建築自体のサイドからの建築の見方にもなろうかと思ったんです。
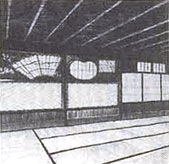
窓の話をもう少しつづけます。窓というのは構造体の余りなんですね。だから構造体の余りがそのまま窓になってるものというのは、非常に明快なんです。そこでは構造体と窓がきれいにぷたつに分かれているんです。おそらく、そういう意味で、簡単に手に入るべニア板を使ったフラードームというのは、余計に深い感銘を受けるわけです。他方、思いっきり構造という制約を離れてしまった場合の窓というのは、恣意的に自由になります。島原・角屋の青貝の間のようになってくるわけです。土壁の中にまったく思うままに窓が開けられているわけです。壁でも開口部でもどちらでもいいところに窓が窓として存在する。そういう意味でフラードームと青貝の間は非常に対極的なところにある。にもかかわらず、窓という意識であるところまでつきつめていくと、窓の通常の意識から離れていくことができるという意味では、両者は、大変似たものであるともいえるという風に思います。

「形態は機能に従う」といいます。窓も機能に従うんです。その機能がいまの時代は多様になってきました。まして、日本はアジアと西洋の接点のようなところですから、多様ということもおぴただしいことになってきます。いずれにせよ単純機能のミース・ファン・デル・ロー工がどう考えただろうかというような点はわからないままに、ミースの時代は終わったんだといえるわけです。そこで、実際に「形態は機能に従う」というのを機能主義のセオリーとして、ミースの方法を拡大させてみました。たとえば窓に托して一軒の家をやってみると、ものすごくたくさんの要素が出てきます。それが「54の窓」という建物です。一階が開業医院で、二、三階が住宅です。
いま、文化の多様化を考えますと、日本とニューョークが一番持ってる。むしろアジアが近いというだけ、東京が一番ではないかと思います。はっきりした構造を持ってなくても、多様なものが集合できるということが、実は新しいひとつの構造なのだといえるぐらいのものじやないかと思います。「54の窓」では、コストの間題もあって、同一のサイズで多様になり、しかもつけたりはずしたりもできるようにということで、鉄のフレームの窓を構造体のコンクリートに取りつけていく方法をとったわけです。室内の間仕切り部分にも同様な部分が出てきますので、結局、全部で一七一通りの同じ四角形が生まれました。四角い天井などもその数に入ってます。その辺から多様性に一種のゲーム的要素が入ってきて、全部少しずつ違えていったわけです。
基準があって、その基準を超えたもの、バリエーションができるということは、工業化、すなわちスタンダードをつくっていく方法としては、非常に正論です。各個人の差異と工業製品の中に備わっているバリエーションを対応させていこうという方法なわけです。自動車にしても、一種類の自動車が何万台も走っているということはあり得ない。かといって一万人いれば一万台異なる車ということもなかなかあり得ない。細かい装備の違いからいえばどれも違ってるといえるのですが、プロダクツをつくっていく側とすれば、およそどれぐらいの多様性でもって、その需要を受けるかという話と、工業化の窓の話は重なってくる。そういう意味で、窓というのは建築の標準化、工業化の間題を一番身近に引き受けてしまったといえます。従って、かつてあった窓の意味みたいなものを建築に投影しにくくなっているわけです。「54の窓」は、そうした意味で東ヨーロッパの共産圏の国の人たちからは多様性と規格性の間題として関心を持たれました。
いまはスラム・クリアランスでなくなりましたが、たとえば広島のかつての原爆スラムが持っていたようなバイタリティとか迫力、つまり住む人が枠を気にしないで生活していた、その中に持っていた日本アパッチ的パワーは、整理されて同一規格化された中からは決して表われないものです。
スラムの伝統は西欧社会よりもアジア社会にずっと強く存在している。だから、ヨーロッパ型の思考から生まれた近代建築とアジアがあるところから相入れなくなってくるのは、そういうバイタリティというか、生活の表れ方の違いだというようにも思います。
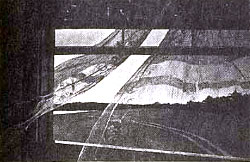
窓について、もう少しつづけますと、たとえばここにある絵があります。描かれているのはたったひとつの窓だけれども、非常に多くのお話をしてくれるわけですね。主人公はどんな人物で、どういう気分でこの窓辺に立っているのか、外の環境はどうなってるのか、人生うまくいってるのか・…といったことを、窓ひとつが語ってくれるわけです。建築の「部分」に、近代的な生産ということとは別に、私たちはいつも余裕を持って触れていなければならないんじゃないかと思います。このアンドリュー・ワイエスの「海よりの風」という絵の窓にしても、窓枠は白いペンキを塗っただけのスタンダードなものです。ところがそこに生活やロマンが出てくる。美しいロマンというわけじゃなく、まったく普通の、どちらかというとちょっと疲れた生活なんですが。ワイエスがいおうとしているものを含めて、ミースがいっていた窓の規格性の間題を取り込んでいくことができる時代になったんじやないかという感じがします。


一九三○年以前、そして一九四五年以降の建築にもっとも大きな影響を与えたのが、ルイス・サリバンの「ウエインライトビル」の窓の考え方です。ちょうどルネッサンスのパラッッオを引き伸ばしたような建物です。その真ん中の部分、伸ばされた胴体の部分に窓が同じになってくるという性格が表れています。そしてこの性格を、上と下を切りはずしてさらに真ん中だけにして用いたのがミースというわけです。そこから現代の私たちの建築が始まっているんです。この問題がいかに大きかったかということは、アルバー・アールトや工−ロ・サーリネンの作品にもよく表れています。たとえばサーリネンのペンシルバニアの寮を見ますと、ぎりぎりの崖っぷちまでいって、最後の一瞬に全部決めちゃったんじゃないかと思われる納まりです。標準化をしながら、しかしなにかしなければならないという気持ちが表れています。
建築家はどうしても進歩的なことが好きで、特に建築のジャーナリズムではその傾向が強くて、庶民の間題から離れてしまうという面がありますが、窓の間題というのは、もっと広く、誰でもが心していることであるし、そうあるべきなんですね。いまや建築のほうには差異がなくて、カーテンの色や外に干してある洗濯物とかで自分の家の窓がわかるというような近代建築になってしまっている。そういうことに対して建築の側から猛然と抵抗していくことも大事なことですね。
S0M設計のヒューストンの「シェル石油本社ビル」では、まったく同じ形の窓を、二重にうねった壁につけています。形は同じなんですが、いろいろに変化して見えるんですね。これなんかはつくるのはかえって大変だったと思うんですが、そういう形で必死に抵抗しているように見えますね。
また、インドのジャイナ教の本山の建物なんですが、白い大理石でつくられていて、窓はそれぞれ多様な形でレースのようになっている。そのレースをもれて入ってくる光がやわらかく均一になっている。その内部に九匹の象が坐っているんですが、まあ、世界にはこういう効果の窓もあるということです。
設計のプロセスにおける考え方のルーツの問題は、雑誌に発表するときにはあまり関係がなくなってしまうものですから、「54の窓」のときもなにか奇抜なものが出てきたという風に受け止められていたと思うんですが、ぼくにとって窓というのが近代建築の表れとしては一番大きい問題だったんです。建築のデザインになったときのズレということに気づいて、それからひとつひとつを学習のテーマとしてやってきたわけです。それ以後も、ぼくの作品はそのつど予想外だという感じで受け止められているんですが、ぼくにとって、こういうエレメントの学習は唯一残された手掛りだったんです。